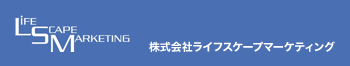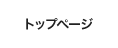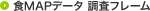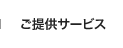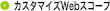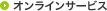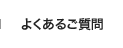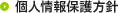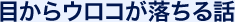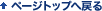弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第80回 日本の食文化再考と創生プロジェクトの紹介
私は日本の食を根本的に考えなおし、それを食卓にデザインするプロジェクトを進めている。
2011年3月11日に起きた東日本大震災は、日本人のこれまでの生活様式(ライフスタイル)を根本から見直すことを迫った天の声かもしれない。グルメの時代は終わっている。
すでに1年半以上の時が流れ、いささか風化し始めた悲惨な体験知~経験知をどう未来に活かすか?
今年の春から日本、米国、仏国(予備として韓国)の一般家庭の食卓調査を実施している。食卓調査は3つの次元で実施されている。
- 食生活意識調査
- 1週間の食卓日記調査(秋と冬)
- 食卓やメニューの写真撮影調査
食卓調査以外に2つの調査を併行して実施している。
- 東京、シアトル、パリ、ソウルの店舗観察調査
- 食品の収集と試食
調査を実施する企画書を出した際、多くの食品企業から「いまさらアメリカやフランスから何を学ぶのか?」の疑問が出された。
ただ次の仮説があった。
- 日本にはない食卓の骨格があるのではないか?
- 移民を受け入れ、自国に同化させる懐の深さがあるのではないか?
- 世界同時進行する食トレンドがあるがあるのではないか?
- 日本以上に個性的な食品の展開が活発ではないか?
私たち日本人は21世紀に入り、海外から学ぶことを忘れ、いささか傲慢になっているように思える。若い世代を中心に内篭りがちになっていることも海外への関心を弱めている。大きな物語の終焉である。これをポストモダン社会と呼ぶ識者もいる。
4カ国の調査の結果(まだ途中段階ではあるが)は、これまでの常識がひっくり返すものであった。
正に「目から鱗が落ちる」である。
現在の日本の食品メーカーは目先のそろばん勘定で海外進出に熱心である。その結果が今回の中国問題である。多くの企業が中国進出に軌道修正を迫られている。
因みにアメリカの食品企業はグローバル企業は別にして、国内市場の開拓に熱心である。その象徴が西海岸の食品スーパーでブームになっている「DISCOVER LOCAL」である。ただし日本のような全国駅弁祭りや物産展ではない。地元州の食品を掘り起こし提供する、地に足をつけた骨太の挑戦である。
今必要なことは、長期的視点で「海外から学ぶ」である。
世界は21世紀に入り軌道を変えている。リーマンショック後、世界の食の潮流は大転換した。その世界潮流を欧米や韓国から学ぶことは、日本の食市場を再考する上で極めて重要である。とりわけ食品メーカーにとって重要である。
人類の食の歴史は食糧の保存と食品の美味しさ実現を両立させる技術革新の歴史であった。発酵食品や魚介の干物が良い例である。野菜の漬物や魚介の干物は生の野菜や魚介とは違った美味しさを作っている。缶詰も技術革新の産物である。冷凍食品は比較的新しい技術革新である。これらの多くは自然の摂理を生かした開発である。
しかし戦後の日本の食品開発は、一転して素材の持ち味や美味しさを犠牲にした技術ばかりである。東日本大震災の経験知と、大転換している世界の食の潮流は、食品開発の根源的療法を要求している。
今回の調査の中から1つの重要な仮説が生まれた。
「食品メーカーが日本の食文化の創生に大きな役割を果たすのではないか」
日本の食品メーカーが日本の食文化に重要なインパクトを与えるだろう。一部の著名な料理人や食研究家のみが日本の食文化のリーダーではない。食品メーカーが日本の食文化創生に深くかかわる時代が来るという仮説である(詳しくは次回に述べる)。日本の食文化創生のヒントは、日本の市民社会が誕生し、成長し始めた明治から大正、昭和(戦前まで)にあると睨んでいる。
数回にわたって日本の食文化再考と創生プロジェクトを簡単に紹介したい。
今回は手始めとして、パリのSIAL(シアル)で、今年10月に開催された世界最大の食の国際見本市を視察した感想を述べたい。
SIALからの報告
食市場創造の法則から外れている日本企業
SIAL2012では5,000近くのブースに100カ国の食品メーカーが参加していた(一部機械メーカーも出展していた)。ドイツのANUGAとフランスのSIALで1年交代で開かれる世界最大級の国際食品産業展である。今年はSIALで開かれた。展示会場は2つの流れがあった。
1つはアジア、アフリカ、中南米、イスラム圏など、西洋圏以外の民族と宗教の食文化の流れ。1つは都市市民や中間所得者層をターゲットにした世界共通の最新の食文化の流れ。
最新の食文化の流れをSIALのリポートでは「SNACKING」と呼んでいた。このキーワードは今後の日本の食を創生する上できわめて重要である(これもいずれお話する)。
2大潮流がクロスオーバーする中で、各ブースでは様々な食品群が展示され、活発な商談が行われていた。
SIALの出展企業のほぼ半数がアジア、アフリカ、中南米、イスラム圏の食品企業である。その中でHALAL(イスラム教)とKOSHER(ユダヤ教)の出展が目立った。会場の資料によるとHALALの世界市場規模は消費者16億人、生産額6,320億ドル、世界の食品工業の15%に達する。年率10%の驚異的な伸び。文化と宗教が入り混じったエスニックフード市場である。
一番気になったのは日本のブースの貧弱さである。会場の半分を占めるアラウンド・ザ・ワールド会場に出展している日本ブースはわずか12ブースだった。ブースに展示されている商品は日本酒や醤油、酢、味噌など伝統的食品ばかり。世界潮流に乗った展示は全くされていなかった。
会場の半分を占めるカテゴリー別のブースでは、世界から集まった食品企業が1つのモノや素材にこだわり、それを様々な用途や商品形態で展開している。これに対し日本企業は単品的で底の浅い展示しかしていなかった。
川上の素材をプロダクトカテゴリーと呼ぶ(ex.トマト、ライス)。世界の食品メーカーは「サプライ視点(供給)」でプロダクトカテゴリー(の入手)にこだわる。
そして加工をする際「オファー視点(提供)」でニーズカテゴリー化し、様々な用途や商品形態の食品を開発する。そしてラインアップ化する。
ラインアップを通じてブランドの木を茂らせる。その結果、売場に面が出来上がり新しい市場カテゴリーが誕生する。
プロダクトカテゴリーとニーズカテゴリーのクロスマッチングが、市場創造の方程式である。
注)「供給」は単に物を流すだけの行為。「提供」は相手に物を差し出し用をたすことで完結する行為。
日本の食品メーカーはこの方程式に当てはまらないケースが多い。その理由の一つがプロダクトブランドよりカンパニーブランドを重視する企業姿勢(風土)である。日本の食品メーカーはブランドの木を育てることができない。
もう1つの理由は川上のプロダクトカテゴリーをコントロールできないためである。大半が商社任せ、国任せである。これでは川上のモノ(素材の入手)にこだわれない。
アメリカ穀物協会が昨年に発表した2040年の東アジアの食市場予測(Food 2040)リポートによると、今後30年で東アジアの食品市場に大きなインパクトを与える事柄として、川上のプロダクトカテゴリー(一次産品)をコントロールする企業の登場が挙げられている。そのほとんどが日本以外の国々(特に中国)である。Food 2040ではその一次産品を「ニッチ作物」とよんでいる。
日本の食品メーカーは大きな試練に立たされている。最大の問題は、この事態の深刻さに対する危機感が薄いことである。「自分がいる間は大丈夫だ」と考えるトップが意外に多いように思える。
自給率100%であり、日本の食文化の代名詞である米(ライス)に関してSIALの強い印象がある。
SIAL会場では米が多く展示されていた。米をベースにした加工食品が続々登場していた。タイのブースではタイ米が8種類展示されていた。その8種類は料理や加工用途の違いを意識している。ジャスミン米は品種改良が進み、より香りの高いジャスミン米が登場していた。
中国のジャポニカ米の生産量は今や日本の6倍である。コストは10分の1である。中国ではジャポニカ米の伸びがインディカ米の伸びを凌駕している。SIALで中国の出展数に目を見張った。おそらく最大の出展数ではないか。中国の食市場に世界が進出しているのではなく、中国が世界の食市場に進出しているのである。米でも日本は大きく出遅れている。
日本のブースでは東北の美しい稲穂風景のポスターの横にあきたこまちの10キロパックが並べられていた。昔ながらの銀シャリの世界である。横には京都の抹茶があった。日本でもあまり飲まれなくなったお茶である。時代潮流を捉える感覚が、日本と世界とでは大きな異なる。
世界はさまざまな米(ライス)に注目している。米を使った加工食品や料理にこだわっている。米を主食にする国、そうでない国を問わずに米の加工に熱心である。米の加工にこだわっていないのは日本だけではないか?うまい銀シャリ世界(一次産品どまり)の呪縛から一歩も逃げられない日本のジレンマが見えた。
市民が主役の食の文明開化のときが訪れている。