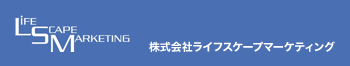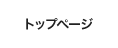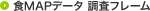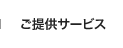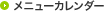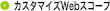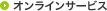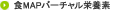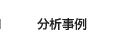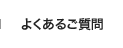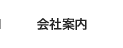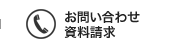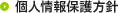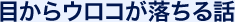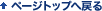弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第76回 美味しさの働き力
料理研究家、辰巳芳子さんは料理の心を次のように言っています。
「美味しさのメリハリの心が大切です」
- 味を活かす
- 味を引き出す
- 味をそろえる
- 味を引き立てる 温度に係わることが多いです。ギンギンに冷やしきったビールは味が引き立てられません。
- 味を抑える
冷蔵庫に入った豆腐の旨味は抑えられます。
働き力1 嫌な臭いを消す
嫌な臭いを消すには物理的作用と化学的作用があります。
物理的作用の一つが味噌による臭い消しです。味噌は魚の生臭み成分(アミン、アンモニア)を吸着します。鯖の味噌煮がよい例です。トマトのペクチンも臭みをとる効果があります。肉の煮込みにトマトを使うと肉の臭みが緩和されます。
牛乳のたんぱく質はコロイド状で肉や魚などの食品の臭みを吸着します。例えばレバーの臭み消しや栗の渋抜きに牛乳を使うことがあります。栗の灰汁は、水で一応処理して、牛乳(粉乳も可)で8分ほど下茹でします。煮汁がねずみ色になり、栗が黄色味を帯びるとさっとすくい上げ、熱湯処理する。タンニンが牛乳のカルシウムで解消され、渋みが抜けます。
化学的作用の代表がpH(酸性度、アルカリ度の程度を表す指標)調整です。臭いの成分(アミン:アルカリ性)は酸性にすると消えることがあります。しょうがの煮魚の美味しさの重要な秘訣が弱酸性にあります。臭いではありませんが、人間はアルカリ性より酸性を美味しく感じます、
pHが7.0未満を酸性(すっぱい)といいます。7.0以上はアルカリ性(味ボケ)といいます。美味しいと感じるのはpH4.0~6.0といわれています。弱酸性であるpH5.5~6.0が一番美味しいといわれています。
料理の味に深みがないとき、隠し味として少量の酢を入れるとpHを下げ、美味しさを感じさせる効果があるといわれています。醤油もpHを下げる効果があります。
梅干はpHを下げ、保存効果を発揮します。酸性になると食物の保存性が高まります。同時に美味しさを感じるpHになります。味の底上げと保存性を高める効果が期待できます。ダシに梅干の酸味を加え火入れして保存するのはそのためです。
人類は食糧の保存に一番力を入れてきました。塩蔵、乾燥、発酵などは古くからある保存技術です。しかもこれらの技術は美味しさづくりに深く関係しています。鯵の干物は生の鯵では出せない美味しさを持っています。漬物も保存技術と美味しさづくり技術が両立しています。牛乳を発酵させてつくるチーズ、牛乳では味わえない全く新しい美味しさです。現在の保存技術であるレトルト技術や防腐材では、保存と美味しさを両立させることは出来ません。現代の加工技術が一番に反省すべき点です。自然の摂理を活かし、素材の持ち味を活かす加工技術が今求められています。
美味しさが吸着してしまうという逆効果もあります。二度温めの味噌汁がまずくなる原因をご存知ですか?
味噌汁の美味しさは味噌の粒子が小さく、ダシの中に均一に浮遊している状態が一番美味しいのです。ところが何度も煮ていると、味噌が大きい粒子になり二つの現象がおきます。
- 美味しさ成分(アミノ酸のうまみ)を吸着してしまいます。
- 味噌の粒子に水の中で浮遊物(寒天性)がくっつき、粒子が大きくなります。
美味しさが損なわれる理由の一つです。
次回は「働き力2 余分な水分を抱える力(保水力)」についてお話します。