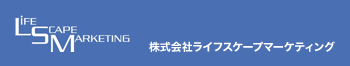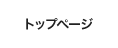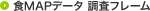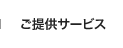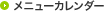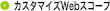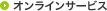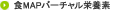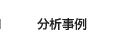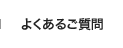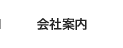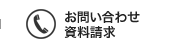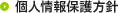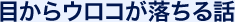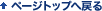弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第74回 美味しさを作る力を科学する ~調理科学を知っていますか?~
日本人としての美味しさを守り、育てるためには、文化としての美味しさの基準が必要です。前回、フランスの味覚週間活動について述べた通りです。
文化としての美味しさとは次の意味です。
人々は「食品を蓄える」というごく日常的な行為の中で、個々の食材の美味しさを向上させる方法を考え、経験から学び、おいしく食べるための工夫を積み重ね、絶えず美味しいものを求めてきました。その経験の歴史は気候・風土と深く関係し、多くの文化と係わってきました。美味しさは生理学的問題であると同時に文化的所産なのです。
美味しさに関しての大ヒット商品を開発したある大手食品メーカーの研究所所長が、10数年前、次のような重要な発言をしました。
「食品メーカーの社会的貢献とは何か? それは全国の消費者に同じ美味しさを届けることである。そしてその役割は果たした。問題はこれからの社会的貢献は何かである。それがまだ分からない」
いまだその答えは出ていないらしい。
私は仮説的に次のように考えました。
「全国の消費者に文化としての美味しさを届ける」
昨今の美味しさ基準の崩壊の危機に対して食品メーカーの責任は大きいです。プロの調理人や料理研究家の美味しさ作りの技が、日常生活に根付かない今日、加工食品を通じて毎日の食卓作りと接点を持つ食品メーカーの役割が大きいからです。にもかかわらず消費者の表面的で流行的な美味しさに迎合しているのが実情です。日本人の美味しさ基準に力点を置いた商品作りや商品提供(=教育提供と呼ぶ)を行うことは大きな意義があると考えています。
話しは変わりますが、美味しさは人それぞれ多様化しており「基準など不可能だ」という人がいます。私も最初はそう思いました。しかし美味しさの研究をしているうちに考えが変わりました。
「日本人の美味しさの基準は作れる」
因みに美味しさの基準は2つの次元があります。
- 美味しさを作る基準
- 美味しさを感じる基準
まずは、美味しさを作る基準から話しをします。
美味しさを評価する基準に関しては多くの理論や実験結果があります。しかし、美味しさを作る機能や効果については種々雑多な雑学しかありません。これを博物学として体系化することで美味しさづくりの基準が作れると考えました。
これを「調理科学」と呼んでいます。
調理科学は台所次元の美味しさづくりの基準です。工場次元の美味しさづくりの基準とは異なります。ただ調理科学をベースに加工次元の美味しさづくりの基準が作れます。図に示すピラミッド構造がそれです。
美味しさづくりの階層ピラミッドは、底辺の調理科学と頂点の加工技術と密接に繋がっていることを表します。美味しさづくりのスタートは底辺の台所次元であり、それがゴールの工場次元になると大きく変質します。台所の小鍋で麺を茹でる際と、プロが大きな釜で麺を茹でる際の工程が大きく異なるのが良い例です。だからこそ台所次元の美味しさづくりをスタートに、両者のギャップを埋めることが大事なのです。調理科学的アプローチが重要になる理由がここにあります。
次回、調理科学について述べます。