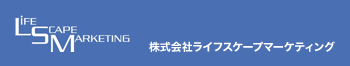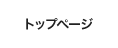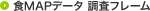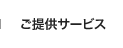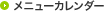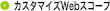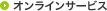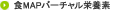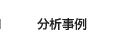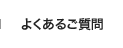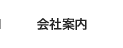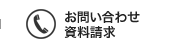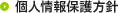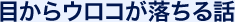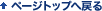弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第70回 火の鳥プロジェクトを立ち上げよう
東日本大震災からはや9ヶ月が過ぎた。
私は、現在「日本の食再考プロジェクト」を10数社の食品メーカーと進めている。
そのきっかけは、アメリカの内食回帰の実情を調べるため、3月11日午後2時45分頃、成田空港で出国手続き中、大震災に被災したことである。1日半成田空港に閉じ込められ、ほとんど飲まず食わずの中、ようやくサンフランシスコ行きのフライトをゲットし、強行渡米した。
そしてアメリカで大震災の爪あとのすさまじさ、福島原発メルトダウンの恐怖、あまりに悲惨な現地の実情をメディアを通じて知り、恐怖感と焦燥感にさいなまされる毎日だった。
「何とかしなければならない」
「このままでは日本は世界から消えてしまう」
さまざまな思いが頭を巡り、
「一体自分は何をしなければならないのか」
を絶えず自問自答していた。
当時の菅政権の対応のまずさに対する情けなさ(私は菅氏の大学1年後輩である)、東電への不信感。情けない彼らだが、彼らほどの力もない私に一体何ができるのか。現地復旧への援助は当然だが、それ以上に次の思いが強かった。
「世界が日本を見ている。かつての阪神大震災後、日本は何も変わらなかった。『喉もと過ぎれば何とか』の日本人の悪い癖がまた出るのではないか。そうすれば世界は日本人を見限るだろう」
戦後始まった日本人の世間主義が怖い。
テレビでCNNの女性ニュースキャスターが、
「被災地のおばあちゃんが、被害者にもかかわらず、私にせんべいをくれた。こんな国民は世界中探してもいない。彼らは皆仏教徒だと聞いている」
と涙ながらにしゃべっていた。しかし私は、
「はたしてそうか?」
と思った。というのも成田で一昼夜、飲まず食わずに過ごした記憶がよみがえったからだ。
ガスも電気もない成田空港の地上ロビーに、立水の余地もないほどの大勢の人々。ろくに水もなく、食べ物は底を突いている。疲労感と言いようのない不安感に皆苛まされている。ときおり航空会社が水と非常食をワゴンにのせて支給する。それを奪うように奪取するのは外国人の旅行客ばかりだ。とりわけアジア系旅行客の行動はまさに襲撃だ。それを日本人は、ただ、だまって見ている。
「なぜ?」
外国人は自分の命は自分で守るという気持ちが強いのではないか。だから人目をはばからず水や食料を奪い合う。日本人は「いずれ誰かが助けに来てくれるだろう」という不思議な安心感が漂い、彼らに何もさせず(受身)、仏のような顔をさせる。昔、あるドイツ人が私に言ったことがある。
「ドイツに来る日本人観光客は、皆ニコニコして、まるで天使の顔をしている」
これは一体褒め言葉なのか?
よく飲み屋で、今の政権の体たらくを非難し、自分の知識を評論家的にひけらかす客がいる。彼らも同じだ。自分は何もせず「誰かよい人がでてくれば日本はよくなる」と、受身的に考える人々だ。そこに自分の意思や実行は存在しない。そんな日本人がやたら多くなった。
「日本人のライフスタイルを変えなければならない」
「ライフスタイルとは何か?」
「ライフスタイルは毎日の生活行動ではないか」
「毎日の生活行動の基本は食生活にあるのではないか」
「そうだ!日本の食生活スタイルを変えれば良いのだ」
そのとき何故か、手塚治虫の「火の鳥」が浮かんだ。手塚の火の鳥は単なる不死鳥ではない。太古の昔から現代を経て、未来にまで進化する不死鳥なのだ。
「日本へ帰って、火の鳥プロジェクトを立ち上げよう」