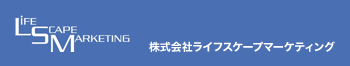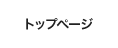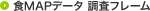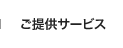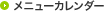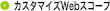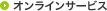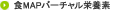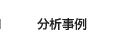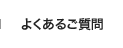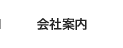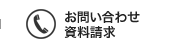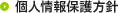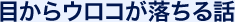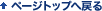弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第61回 伸びるメニュー、縮むメニュー
9月に「天ぷらにソースをかける日本人」を家の光協会から出版しました。この本は食MAPから日本の食卓を生態学的に分析した報告書です。
特に注目は2点あります。
- 日本の食卓には文化が残っている
- 21世紀に入り食卓の潮目が大きく変わろうとしている
そこで、本書の一部を紹介しましょう。「第8章 食卓の10年トレンドと嗜好の変化」の抜粋です。
ロング成長メニューの牽引者は誰?
食MAPによれば2009年、夕食には5.9品のメニュー数が並んでいました。10年前の2000年は7.2メニューでした。毎年少しずつ減り続け、 10年間で1.3メニュー減りました。朝食も昼食も同じように減っています。ただし、1メニュー当たりの使用食材数は減っていません。むしろ増加気味です。
2000年の1メニュー当たり2.7品から2009年では2.9品と、わずかに増加しています。ちなみに、1メニュー当たりの食材数が予想外に少ないと思われる方もいるでしょう。これは、メニューに飲料やアルコール、デザートも入っているためです。惣菜や弁当、作り置き料理も材料1品とカウントされます。
1つの料理にたくさんの種類の食材を使い、食卓の皿数は少なくする----。そんな家庭が増えています。私は「食卓の丼化・鍋化現象」と呼んでいます。この 10年間でどんな料理が増えているか、また減っているかを調べたところ、図表にまとめることができました。これを基に、ロング成長型料理を牽引している消費者はだれなのか、逆に減り続けている低迷型料理はどんな消費者が原因なのか、迫っていくことにします。
図表1 10年間成長している料理
| 1.純和風料理ではない野菜料理 | 倍率 | 2.牛肉以外の肉と野菜を使う料理 | 倍率 |
| 野菜炒め | 1.45倍 | 豚肉のポトフ | 5.76倍 |
| 野菜サラダ | 1.44倍 | 豚肉の冷しゃぶ | 1.86倍 |
| 豚肉のキムチ炒め | 1.41倍 | ||
| ひき肉と野菜のはさみ揚げ | 1.14倍 | ||
| 鶏肉と野菜の中華炒め | 1.12倍 | ||
| 豚肉と野菜の和風炒め | 1.04倍 | ||
| ロールキャベツ | 1.03倍 |
| 3.経済的な肉(鶏肉、ひき肉)を使った料理 | 倍率 | 4.種類の幅を広げた人気料理 | 倍率 |
| 肉豆腐 | 2.14倍 | その他鍋 | 4.88倍 |
| 煮込みハンバーグ | 1.28倍 | その他ご飯 | 2.93倍 |
| チキンソテー | 1.23倍 | その他麺 | 2.38倍 |
| マーボー豆腐 | 1.22倍 | その他スパゲッティ | 2.06倍 |
| ハンバーグ | 1.10倍 | その他スープ | 2.02倍 |
| その他丼 | 1.78倍 |
| 5.体にやさしい飲み物 | 倍率 | 6.食事を楽しくする経済的な酒 | 倍率 |
| 豆乳 | 6.05倍 | 梅酒・果実酒 | 1.76倍 |
| 抹茶 | 2.66倍 | 焼酎 | 1.11倍 |
| 野菜ジュース | 1.68倍 | ||
| 紅茶 | 1.21倍 | ||
| ミネラルウォーター | 1.19倍 | ||
| ジャスミン茶 | 1.14倍 |
図表2 10年間低迷している料理
| 1.和風(醤油)料理 | 倍率 | 2.カロリーの高い料理 | 倍率 |
| おひたし | 0.94倍 | ソース焼きそば | 0.92倍 |
| 刺身 | 0.82倍 | 市販弁当 | 0.87倍 |
| 漬物 | 0.55倍 | 鉄板焼き | 0.85倍 |
| 佃煮 | 0.51倍 | とんこつラーメン | 0.78倍 |
| 山芋のとろろ | 0.51倍 | 天丼 | 0.74倍 |
| 大根おろし | 0.32倍 | トンカツ | 0.73倍 |
| エビフライ | 0.72倍 | ||
| 天ぷらうどん | 0.67倍 | ||
| 肉コロッケ | 0.67倍 | ||
| ビーフシチュー | 0.63倍 | ||
| カツカレー | 0.62倍 | ||
| フライドチキン | 0.62倍 | ||
| ビーフカレー | 0.60倍 | ||
| カツ丼 | 0.60倍 | ||
| ピラフ | 0.57倍 | ||
| フライドポテト | 0.55倍 | ||
| ハンバーガー | 0.41倍 |
| 3.純和風の野菜料理 | 倍率 | 4.「晩酌の友」型料理 | 倍率 |
| かぼちゃ煮 | 0.79倍 | 茹で枝豆 | 0.84倍 |
| 野菜のあん炊き | 0.67倍 | 湯豆腐 | 0.67倍 |
| きんとん | 0.54倍 | 冷やしトマト | 0.63倍 |
| なす油焼き | 0.40倍 | シシャモ焼き | 0.59倍 |
| ぜんまい煮物 | 0.22倍 | 生ウニ | 0.32倍 |
| イカの塩辛 | 0.32倍 |
| 5.間食型メニュー | 倍率 | 6.自家製の健康飲料 | 倍率 |
| 緑茶 | 0.78倍 | 自家製ジュース | 0.66倍 |
| 100%果汁飲料 | 0.73倍 | ||
| 牛乳 | 0.65倍 | ||
| ウーロン茶 | 0.46倍 | ||
| 100%未満果汁飲料 | 0.32倍 | ||
| 菓子類 | 多数 |
ロング成長型料理と低迷型料理について、それぞれ7つの料理を取り上げ、モニターの年齢と家族形態別(夫婦のみ世帯、夫婦と子供世帯)の10年間のTI 値の推移を分析しました。取り上げた料理は、ロング成長型が煮こみハンバーグ・マーボー豆腐・その他鍋(カレー鍋など)・野菜炒め・豚肉と野菜の和風炒め・野菜サラダ・豆乳、低迷型はソース焼きそば・エビフライ・天ぷらうどん・肉コロッケ・ビーフカレー・刺身・漬物です。すると、興味ある事実が浮かび上がりました。
- ロング成長型料理は、ほとんどの世帯で増えている
- 低迷型料理は、夫婦と子供の世帯で低迷し、夫婦のみ世帯が下支えしている
ロング成長型料理のTI値を2000年と2009年で比較すると、その他鍋(カレー鍋など)、野菜炒め、豚肉と野菜の和風炒め、野菜サラダ、豆乳は、全ての世帯で増えています。煮こみハンバーグは20代、50代以上の夫婦のみ世帯で伸び悩んでいますが、他の世帯で増えています。マーボー豆腐は20代、 30代の夫婦のみ世帯で伸び悩んでいますが、40代、50代以上の夫婦のみ世帯で増えています。
どの家庭でも増えるということは、共通した増える要素があるわけです。図表①の6つの食卓潮流がその共通要素であり、各世帯に支持されている傾向なのでしょう。
低迷型料理は多くの場合、夫婦と子供のいる世帯で減少しています。一方、夫婦のみ世帯で増えている料理があります。
- ソース焼きそばとエビフライは20代、40代の夫婦のみ世帯で増えています。
- 天ぷらうどんは、30代、40代の夫婦のみ世帯で増えています。
- 肉コロッケは30代、40代、50代の夫婦のみ世帯で増えています。
- ビーフカレー40代の夫婦のみ世帯で増えています。
- 刺身は40代、50代の夫婦のみ世帯で増えています。
- 漬物だけ、全ての世帯で減少しています。
この結果から意外なことが分かりました。
「子供が低迷型料理をつくる原因」
低迷型料理の多くはカロリーの高い料理です。カロリーの高い料理は子供や若い世代が好む料理のはずです。その料理が子供のいる世帯で減少しているわけです。食卓の動機から「子供の好きな料理を出した」の回答割合が減っているかを調べたところ、子供の好きな料理を出す傾向は減っていません。どうやら子供自身がカロリーの高い料理を敬遠しているようです。カロリーの摂りすぎを気にする若い世代が増えているためでしょう。健康やダイエット情報などに敏感な若い世代は、人一倍に美味しさを頭で感じるようです。いずれにしても次のことがいえます。
「少子高齢社会では、子供は食卓の鎹(かすがい)にならない」
この事実、言葉を代えれば「食卓のリーダーは中高年の夫婦のみ家庭が握る」ともいえるかもしれません。
夫婦のみ世帯でカロリーの高い料理が必ずしも減っていません。歳をとればカロリーの高い料理から低い料理に嗜好が移るというのが常識でした。しかし、実際は必ずしもそうでは無いようです。
アメリカではかつて「安定食品」に関する研究が盛んに行われました。子供の頃からハンバーガー好きなアメリカ人は、歳をとっても嗜好が変わらないという研究です。これに対し、日本人は若い時の嗜好が歳をとると変わると考えられていました。しかし、最近の日本人には「安定食品」があるようです。それが子供という壁がない夫婦のみの世帯で顕著なのではないでしょうか。
人は物心ついたころや育ち盛りのころに親しんだ料理・食品の味を記憶しています。そして何かの緊張した時に、人は安定食品を求めます。例えば海外旅行中、無性に味噌汁が恋しくなったり、日本料理が食べたくなったりすることがあります。安定食品とは食べると精神的に安心が得られる食品です。
低迷型料理の多くは、40代、50代以上の世代が若い頃によく食べた料理です。子供がいないことが、彼らの嗜好を若々しくしているのかもしれません。子供がいない世帯では、毎日とはいわないまでも、安定食品が食卓を賑わしているのではないでしょうか。少子高齢時代の食卓のリーダーは、案外にエルダー世代なのかもしれません。
以上が抜粋です。ご興味あるかたは是非、小本をご一読ください。因みに、本のタイトルの天ぷらとソースにかかわる重大な事実も分かりました。是非、お確かめください。
ちょっと宣伝が過ぎますか?