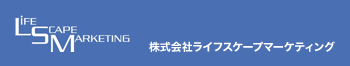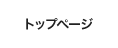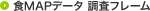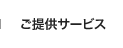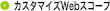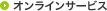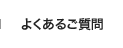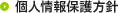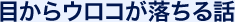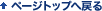弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。
第9回 コロンブスの卵理論
 今年の正月7日、読売新聞が「縮む胃袋」と題し、食品の市場縮小を特集していました。食品メーカーと飲食店、食品関連流通業を合わせた食品産業の市場規模が、1998年度の93.1兆円をピークに、2005年度には85.4兆と8兆円も落ち込んだという記事です。縮む食市場に対して食品業界は業界再編成や異分野との提携戦略に躍起になっているという内容の記事でした。
今年の正月7日、読売新聞が「縮む胃袋」と題し、食品の市場縮小を特集していました。食品メーカーと飲食店、食品関連流通業を合わせた食品産業の市場規模が、1998年度の93.1兆円をピークに、2005年度には85.4兆と8兆円も落ち込んだという記事です。縮む食市場に対して食品業界は業界再編成や異分野との提携戦略に躍起になっているという内容の記事でした。
一方、こんなデータもあります。現在の日本人の1日当たりの摂取カロリーは、供給量ベースで2600キロカロリーです。しかし消費量ベースでは1800 キロカロリーです。実に800キロカロリーが無駄に捨てられている勘定です。この2つの事実を重ね合わせて考えると、私たちは毎日の食生活を根本的に見直す時期に来ているのではないでしょうか。少なくとも次のことは言えます。
「飽食の時代は終わった」
1月の下旬、筆者のところにある会社のトップから電話がありました。このトップは牛肉のエージング技術の優秀さで話題になり、有名な週刊誌にご本人の写真入で紹介されたほどの熱心な食の研究家です。電話の先でやや興奮ぎみの氏曰く
「食糧危機を解決する方策がわかった。まさにコロンブスの卵だ。それを今、実験している。君なら理解してくれるはずだ。1度来てくれ」
話しを聞いているうち、私は彼が常日頃から研究開発している調理法が関係していると直感しました。その時、辰巳芳子さん「味覚旬月」(ちくま文庫)の中の「女の力~梅仕事」の1節を思い出しました。
「梅仕事」、優しくも緊張感を含む、心地よい呼び名であった。 母の書いたものに、ほんとうの梅仕事は「花の終わったあとのお礼肥え、虫退治、消毒、盛夏の剪定に始まる」とある。段取りは、頭の中にぴったり収まっており、時が来ればたぐり出し、用意が良かった。 これにつるびて、赤紫蘇、生姜のことも忘れなかった。 ~ 中略 ~ 赤紫蘇が芽を出したのだ。紫蘇の世話は、まず芽じそをせっせと間引いてたべることから始まる。青紫蘇と赤紫蘇の芽、あるかないかの根をつけている双葉。赤・青あいまぜにして、鰹や鯵のたたきのつま、酢のもののけん、日々のサラダ。とにかく惜しまず使い、欲しがるかたがあれば、さしあげられるだけお分けする。 やがて、見込みあるものの間隔をとり、1本立ちにしてやる。これにどんどん堆肥や油かすをやる。50~60センチほどの丈になったら芯をつむ。これで脇芽がのびてくる。 脇芽が十分に育ってきたら、これもとめる。すると孫芽が育つ。こうして、次々と新芽をふやす。収穫しながら育てる方法で、1本の木から5本分ほどの収穫を得る。 赤紫蘇は、茎まで抜いて束ねた姿で世にでているが、あれでは、こわい葉、柔らかい葉も一緒くたで、上等のゆかりはできない。
さっそく電話の先のトップのところへ行き、彼の考えと開発された食品や料理を試食しました。彼が研究開発しているのはデオキシ・クッキング(酸化還元調理法)です。加熱という調理に伴う酸化を防ぐ調理法です。彼曰く...
「生鮮品の多くにポリリン酸化合物という薬品が使われており、これがデオキシ・クッキングの邪魔をする」
私も知らなかったことですが、ポリリン酸化合物は多くの鮮魚や精肉に使われており、発色をよくし、鮮度を保ちます。彼いわく、
「これを使うと鮮度がたもたれているように見えるが、味も風味も台無しになってしまう」
そのため彼はポリリン酸化合物が使われていない鮮魚を、鳥羽の漁港から直接仕入れ、デオキシ・クッキングを行っているのです。私は鳥羽の地元から直送された小魚を食べました。まるで獲れたばかりの鮮度と食感・風味の煮魚でした。内蔵も食べました。実に美味い。驚いたことにその小魚は冷凍魚だったのです。彼の調理法を使えば、冷凍の魚でも丸ごと食べられます。しかも新鮮そのものです。内臓が丸ごと食べられる冷凍魚は驚きです。
この調理法で料理したご飯をいただきました。良く噛むことで確かに美味しさが伝わってきます。彼いわく「よく噛むことで食べる量が少なくても十分な満足感が得られる」。彼によれば食料費が3分の1で済むとのこと。だから食糧問題が一挙に解決するというのが、彼のコロンブスの卵理論です。
日本人の1日当たりの無駄にしている熱供給量は3分の1、辰巳芳子さんが土地と関わりあう紫蘇の収穫量は市販の紫蘇の5倍。彼の推奨しているコロンブスの卵理論で調理すると3分の1の食費。一度試してみる価値はありそうです。食生活日記の料理レシピにも加え、食の達人のみなさんに実践してもらいたいです。