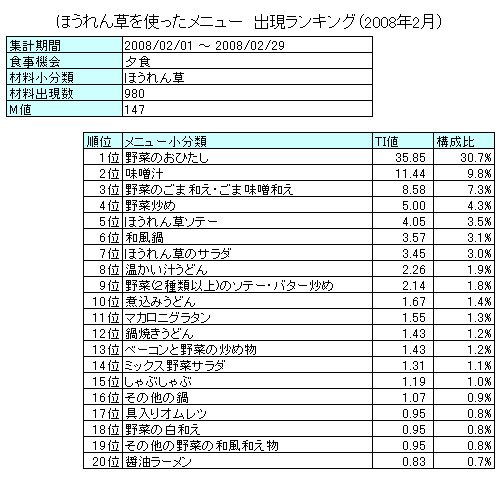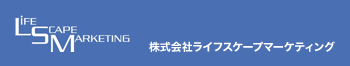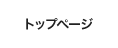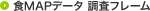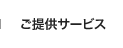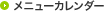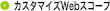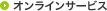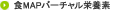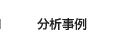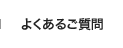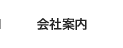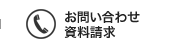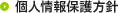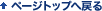第37回 ほうれん草
 寒い外から帰ってきて、鍋物がおいしいと思う時期ですね。鍋物の材料としても登場しますが、冬になるとおいしさが一段と増し、緑黄色野菜の中でもっともポピュラーな「ほうれん草」を今月は取り上げます。
寒い外から帰ってきて、鍋物がおいしいと思う時期ですね。鍋物の材料としても登場しますが、冬になるとおいしさが一段と増し、緑黄色野菜の中でもっともポピュラーな「ほうれん草」を今月は取り上げます。
「ほうれん草」の歴史
はっきりとした原産地はわかっていないようですが、英語の語源からアフガニスタンかイランとされています。中世の時代にヨーロッパに伝わり、品種改良されて西洋種の「ほうれん草」がつくられ、シルクロードを通って東アジア、中国に広まったとされています。この中国で東洋種の「ほうれん草」に改良されました。日本には、17世紀に中国から東洋種が、19世紀にフランスから西洋種が伝わったようです。
「ほうれん草」の品種と産地
主に、東洋種、西洋種、交配種、サラダ用の4つの品種があります。東洋種は、葉の先がとがり、のこぎりのような切れ込みがあり根がピンク色です。甘味が強いのですが、栽培に手がかかるので収穫量が減っています。西洋種は、葉が大きく丸みがあり肉厚、根は緑色です。暑さに強いため、収穫量が多いのですが、あくが強いのが特徴です。海外では主に缶詰にするようです。交配種は、東洋種と西洋種を交配したもので、東洋種の甘味を残しながら収穫量のある品種です。今では、日本で主流の「ほうれん草」です。サラダほうれん草はあくが少なく生食にむいた新しい品種です。水耕栽培されます。産地は、夏から秋にかけては北海道、秋から春までは千葉、年間を通しては群馬が多いようです。
編集後記
 今回は、「ほうれん草」の定番であるお浸しにしようと思いましたが、醤油を直接かけて食べるのが苦手なので、いつも作っている和え物にしました。このほうが塩分も控えめで食べやすいからです。夏に見かける「サラダほうれん草」を、みなさんは食べたことがありますか? 「ほうれん草」を生で食べるの? と思いましたが、実際に食べてみるとおいしくて驚きました。夏に見かけたときは、是非食べてみてください。
今回は、「ほうれん草」の定番であるお浸しにしようと思いましたが、醤油を直接かけて食べるのが苦手なので、いつも作っている和え物にしました。このほうが塩分も控えめで食べやすいからです。夏に見かける「サラダほうれん草」を、みなさんは食べたことがありますか? 「ほうれん草」を生で食べるの? と思いましたが、実際に食べてみるとおいしくて驚きました。夏に見かけたときは、是非食べてみてください。