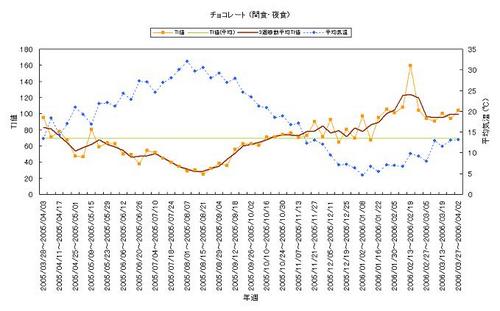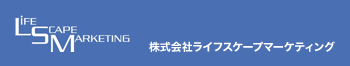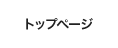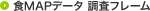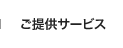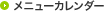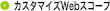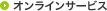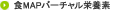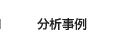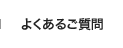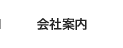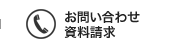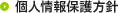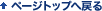第25回 バレンタインデー
 成人式が過ぎた頃から、お店で目に付くのは、バレンタインデーのチョコレートですね。「バレンタインデー」については、この「食彩事記」第一話で「由来」を書いていますので、ここでは、チョコレートの歴史などで、話を進めていきます。
成人式が過ぎた頃から、お店で目に付くのは、バレンタインデーのチョコレートですね。「バレンタインデー」については、この「食彩事記」第一話で「由来」を書いていますので、ここでは、チョコレートの歴史などで、話を進めていきます。
古代メキシコのチョコレート
古代メキシコでは、チョコレートの原料であるカカオ豆を、紀元前1000年頃から栽培されていたといわれています。カカオ豆のことを「カカオトル(苦い汁の意味)」とよび、この「カカオトル」で作った飲み物を「ショコラトル」といい、チョコレートの語源になりました。非常に苦い飲み物でしたが、1500年代に、スペインに伝わった際に、砂糖を入れて飲むことが考えられました。
チョコレートの渡米
スペインから、1600年代にイタリア人がチョコレートの製法をイタリアに伝え、さらに、スペインの王女アンナがフランスのルイ13世に嫁いで、フランスにチョコレートを飲む習慣を伝えました。これを機会に、ヨーロッパに広がったようです。そして、19世紀にチョコレートの製造会社が続々誕生しました。ヴァン・ホーテンのように現在まで続いている会社も生まれました。この時期、「チョコレートの4大発明」といわれるものがあります。
「チョコレートの4大発明」
- ココアパウダー...最初にオランダのヴァン・ホーテンが発明。カカオ豆の脂肪分を半分にして、お湯に溶けやすくなる。ダッチプロセス(ココア豆をアルカリで中和)と呼ばれ、ココア製法の基礎。
- イーティングチョコレート...イギリスで、ココアパウダーの製造で余ったココアバターから、固めることが考えられ、「飲むもの」から食べるチョコレートが誕生。
- ミルクチョコレート...スイスで、苦味のあるイーティングチョコレートに、ミルクが加えられマイルドな味となる。
- コンチングマシン...スイスで、砂糖の粒子を細かくする機械が発明され、さらに、なめらかな感触のチョコレートが誕生。
日本でのチョコレート
最初にチョコレートを体験した日本人は、1617年に伊達政宗の密命でスペインにいった支倉常長(はせくらつねなが)の一行とされています。そのあとは、 1873年に岩倉全権大使団一行がフランスのリヨンで、チョコレート工場を見学して食べたとされています。4年後には、東京米津風月堂が「千代古齢糖」を売り出しました。しかし、「血汚齢糖といい、牛の血で固めて作ったお菓子」と、「牛の乳」が「牛の血」と伝わったため普及はしなかったようです。普及は、 1918(大正7)年に森永製菓が、アメリカから製造施設を輸入、1926(大正15)年に明治製菓がドイツから製造施設を輸入して、チョコレートの量産が始まってからです。
編集後記
 年々、チョコレートは、たくさんの種類を見かけます。お店でのチョコレートめぐりも楽しいものです。バレンタインデーの時期には、贈るチョコレートよりも、自分が食べたいチョコレートを少し奮発して購入します。皆さんはどうでしょうか?
年々、チョコレートは、たくさんの種類を見かけます。お店でのチョコレートめぐりも楽しいものです。バレンタインデーの時期には、贈るチョコレートよりも、自分が食べたいチョコレートを少し奮発して購入します。皆さんはどうでしょうか?