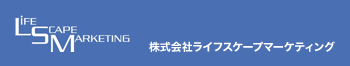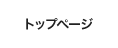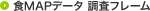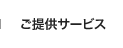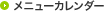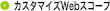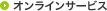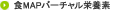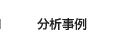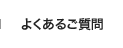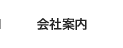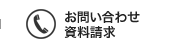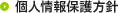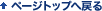第22回 勤労感謝の日
 11月に入り、朝晩と暖房の恋しい日が続くようになりました。
11月に入り、朝晩と暖房の恋しい日が続くようになりました。
今回は、国民の祝日である11月23日の勤労感謝の日から、話を進めたいと思います。
「勤労感謝の日」の由来
1948年に、国民の祝日に関する法律で、「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日」として、11月23日を「勤労感謝の日」と制定されました。戦前は「新嘗祭(にいなめさい)」といい、新米を神殿に供えていました。最近では、日本フードサービス協会が、家族で外食することの楽しさを知ってもらおうと、1984年に「外食の日」としました。
「新嘗祭(にいなめさい)」の由来
新嘗祭の歴史は古く日本書紀に記録があるそうです。戦前は、その年に収穫された穀物(新穀)を神に勧め神を祭る行事として、「天皇が新穀を天神地祇に進めて神を祀り、みずからも食す」儀式でした。
戦後は、皇室典範の行事からははずされましたが、重要な宮中行事として継続されています。儀式は、23日の夕方から始まり翌未明まで行われます。このような収穫を祝う性格の強い勤労感謝の日の前後には、各地で収穫祭や農業祭が行われています。神社の秋祭りもそのひとつです。海外でも収穫を祝うイベントはいろいろあるようですが、アメリカの感謝祭がそれにあたります。1620年にマサチューセッツに上陸した清教徒が最初に秋の収穫を祝ったことに由来するそうです。毎年11月の第4木曜日とされています。
「新豆」
新米はすでに出回っていますが、豆にも旬があることを知っていますか?豆も米と同様年中あるものなので、ピンと来ないかもしれませんが、新豆の採れる11 月から12月にかけてが、一番おいしい季節なのです。そこで今月の「編集後記」は、米と豆を使った赤飯について書きます。
編集後記
 「日本のお祝いに欠かせない料理」
「日本のお祝いに欠かせない料理」
11月15日の七五三や誕生祝などの吉事に欠かせない料理に、赤飯があります。もち米に小豆やささげを1~2割混ぜて蒸し上げるのが正式です。現在では、炊飯器で炊くのが多いようですが、その場合は仕上がりがべたつきやすいので、うるち米を1~2割混ぜるのが一般的です。最近は、スーパーやコンビニでも手軽に購入できるので、家庭で料理をする割合が減っているのではないかと思います。赤飯にも地方色があるようです。
関東地方では、小豆は皮が破れやすいことから縁起が悪いとされ、ささげを使用することが多いようです。私の出身の北海道では、小豆を使った赤飯のほかに甘納豆(金時豆)を使った甘みのある赤飯もあります。また、ゴマ塩を振りかけますが、そのゴマも切ったり炒ったりすると縁起が悪いとされ、そのまま使います。北海道ではゴマ塩のほかに必ず紅生姜が添えられています。皆さんのご家庭ではどうでしょうか?